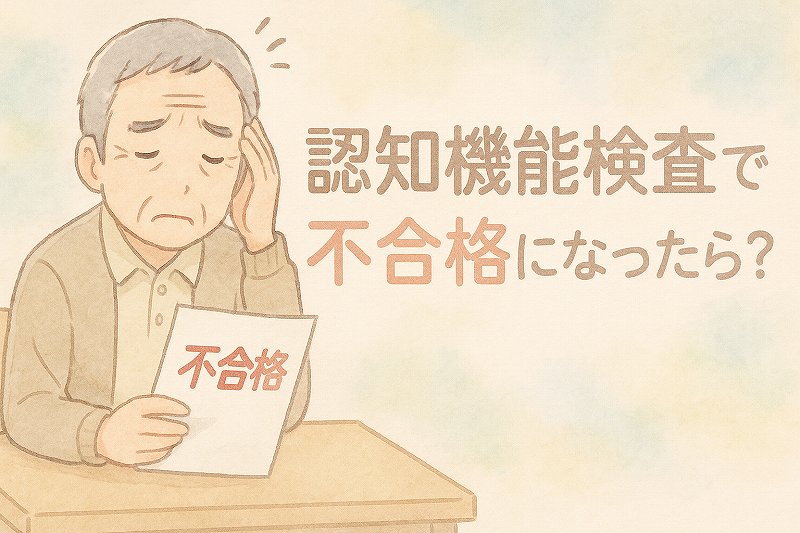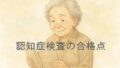認知機能検査で不合格になると、運転免許の更新はできません。
ただし、不合格=即免許取り消しではなく、医師の診断や再検査、実技試験など、復活の道も用意されています。
本記事では、認知機能検査に落ちた後の流れや再チャレンジの方法、家族の対応までをわかりやすく解説します。
大切な免許と暮らしを守るために、今すぐ知っておきたい情報をまとめました。
不安を希望に変える第一歩として、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
認知機能検査で不合格になったらどうなる?影響と流れを解説
認知機能検査で不合格になったらどうなる?影響と流れを解説します。
それでは詳しく見ていきましょう。
①不合格=即失効ではない
認知機能検査で不合格になっても、「はい、即アウト!」というわけではありません。
75歳以上の高齢者が免許更新時に受けるこの検査ですが、不合格になった時点では、まだ免許の効力は残っています。
ここで重要なのは、不合格=「認知症のおそれあり」と判断されること。
その判定が出ると、次のステップとして、医師の診断書を警察(公安委員会)に提出する必要が出てきます。
この診断の結果しだいで、免許が更新できるか、取り消されるかが決まる流れになっているんですね。
②「認知症のおそれあり」と診断されるとどうなる?
2022年5月の法改正以降、認知機能検査の判定結果は非常にシンプルになり、「認知症のおそれあり」か「なし」の2つに分けられます。
| 判定区分 | 検査結果の意味 | 次に行う手続き |
|---|---|---|
| 認知症のおそれなし(合格) | 記憶力・判断力に問題なし | 高齢者講習を受講し免許更新へ |
| 認知症のおそれあり(不合格) | 記憶力・判断力の低下が見られる | 医師の診断書を提出し判断を仰ぐ |
つまり、不合格というのは「認知症のおそれあり」とされた場合のことです。
この段階で本当に認知症と診断された場合は、免許更新ができない可能性が高くなります。
でも逆に、医師の診断で「認知症ではない」と判断されれば、免許の更新が可能になることもあるんですよ。
だから、「不合格=終わり」ではなく、ここからが再チャレンジの始まりでもあるんです。
③医師の診断が必要になるケース
「認知症のおそれあり」と判定された場合、公安委員会から「医師の診断書を提出してください」と連絡があります。
ここで診察を受けて、「認知症ではありません」と診断された場合は、運転技能検査を受けることで免許更新の道が開けます。
でももし、「認知症と診断された」場合は、残念ながら運転免許を維持するのは難しくなってしまいます。
診断書の提出期限も設けられているので、早めに主治医や専門医に相談して準備しておくことが大切です。
特に「もの忘れ」や「集中力の低下」で不合格になった人は、日常的な体調の影響もあるので、医師による丁寧な確認が鍵になりますよ。
④免許停止や取り消しの可能性
医師の診断書で「認知症」と正式に判断された場合、公安委員会は運転免許の「取り消し」や「停止」の処分を行うことになります。
これはもう法律上の義務なので、避けることはできません。
ただし、診断内容によっては「6か月停止」などの軽減措置がとられるケースもあります。
また、診断書の内容に納得できない場合や、認知症ではないという別の医師の診断が得られた場合は、「異議申し立て」や「再提出」も可能です。
つまり、ここであきらめてしまうのはもったいない!しっかり行動すれば、まだ道は残っていることも多いですよ。
最も大切なのは、「不合格でも冷静に、正しい流れで対応すること」。焦らず、一つずつ進めていきましょうね。
再検査や診断書で復活できる?不合格後の対応方法
再検査や診断書で復活できる?不合格後の対応方法について詳しく解説します。
では順番に見ていきましょう。
①認知機能検査を再受検
実は、認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定されても、もう一度、認知機能検査を再受検できますが、受ける度に手数料がかかります。
また、再検査を希望する際は、警察署や運転免許センターに問い合わせてみてください。
「緊張して答えられなかった」「体調が悪かった」といった理由の時もあるので「1回落ちた=終わり」とは限らないので、まずは相談してみましょう。
②専門医の診断で覆ることもある
再検査の代わりに、あるいはそれ以上に重要なのが、専門医による診断書の提出です。
認知機能検査で「おそれあり」と出た場合でも、**専門の医師が『認知症ではない』と判断すれば、運転は続けられる可能性があります。**
この診断書は、かかりつけ医ではなく、「認知症の診断ができる医療機関」で発行されたものでなければなりません。
具体的には、神経内科や老年精神科などが該当します。
診断の結果が免許の命運を握ることになるので、信頼できる医師を見つけて、しっかり検査してもらうことが大切ですね。
③運転技能検査(実車試験)での判断
医師の診断で「認知症ではない」と判断された場合、その次のステップが「運転技能検査」です。
これはいわゆる実技試験で、教習所や免許センターなどで実際に運転をしてもらい、安全運転が可能かどうかをチェックされます。
内容は基本的な運転操作から判断力、反応の速さまで、現実の運転に即した内容になっています。
試験に合格すれば、晴れて免許の更新が可能になります。
「年だから運転は無理だろう」なんて思わず、技術に自信があるならぜひ受けてみてください。
しっかり準備して臨めば、合格する高齢ドライバーもたくさんいますよ!
④手続きの流れと必要書類
では、実際に不合格→復活までの流れをざっくりまとめてみますね。
認知機能検査を再受検以外の場合です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①臨時適性検査 | 「認知症のおそれあり」と判定された場合、医師の診断書が必要 |
| ②医師の診断 | 認知症ではないと診断されれば、次の段階へ |
| ③運転技能検査 | 実際に車を運転し、安全に運転できるか確認 |
| ④免許更新 | すべてクリアすれば、免許更新が可能に |
必要書類としては以下のようなものが必要になります:
- 公安委員会指定の診断書用紙(病院で記入)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 診察費(保険診療または自費)
病院の予約が必要だったり、診断までに日数がかかることもあるので、できるだけ早く動き出すのが大事ですよ。
「まだ間に合う!」という気持ちを持って、しっかり準備していきましょう!
免許を失ったらどうする?高齢者がとれる3つの選択肢
免許を失ったらどうする?高齢者がとれる3つの選択肢について紹介します。
運転できなくなっても、安心して生活を続けるための手段はあります。
①公共交通機関へのシフト
まず考えたいのが、電車やバス、タクシーなどの「公共交通機関」を活用する生活スタイルへの切り替えです。
特に都市部では、駅やバス停が多く、時間も正確なので、意外とスムーズに生活できる場合も多いです。
さらに高齢者向けの「割引パス」や「乗り放題定期」なども各自治体で用意されているので、使わない手はありません。
「バスはわかりにくい…」という方も、最近はスマホのアプリや時刻表を簡単に調べられるサービスもあります。
少しずつ慣れていけば、「運転しなくても大丈夫だった!」と実感できるようになりますよ。
②家族による送迎や支援制度の活用
次に考えたいのが、家族や近所の人に協力をお願いすることです。
特に買い物や病院への通院など、「たまにの用事」なら、頼れる人がいればとても心強いですよね。
それに加えて、各自治体では「移動支援サービス」や「福祉タクシー券」など、高齢者向けのサポート制度も充実しています。
たとえば、送迎付きの買い物バスや、病院に行くための車を用意してくれる地域もあります。
「迷惑をかけたくない…」と思う気持ちも分かりますが、今は社会全体で支える仕組みがどんどん整ってきています。
困ったらまず、市役所や地域包括支援センターに相談してみてくださいね。
③免許返納で得られる特典とは?
「運転はもういいかな…」と感じたら、自主的に免許を返納するという選択肢もあります。
しかも今は、返納することで受けられる「特典」がたくさんあるんです。
| 特典の種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 交通機関の割引 | バス・タクシー・電車の割引やフリーパス |
| 買い物サポート | スーパーの宅配割引や移動販売 |
| 行政の支援 | お出かけ支援券、デマンドバスなど |
返納後には「運転経歴証明書」が発行され、これが身分証明としても使えます。
しかもこの証明書を見せることで、さまざまな施設やお店で高齢者優待を受けられるんですよ。
「車を手放す=不便になる」ではなく、「生活スタイルを変えることで、安心を手に入れる」という考え方もアリです!
大事なのは、自分に合った方法を選び、無理なく、そして安全に暮らしていけるようにすることです。
家族がすべきサポートとは?親が不合格だった場合の対応
家族がすべきサポートとは?親が不合格だった場合の対応について解説します。
親が「認知機能検査に落ちた」と聞いたとき、家族としてどう対応すればいいか、悩みますよね。
でも、ちょっとした気配りや言葉がけで、気持ちも状況もぐっと変わってきますよ。
①まずは本人の気持ちに寄り添う
不合格の結果を聞いた本人は、「もうダメなのか」「恥ずかしい」「家族に迷惑をかけたくない」といった思いでいっぱいかもしれません。
そんなときに「だから言ったじゃない」「やっぱり無理だったか」と言ってしまうと、心に大きな傷が残ってしまいます。
まずは、「びっくりしたね」「緊張してたんだよね」と、気持ちに寄り添う声かけをしてあげてください。
高齢になっても、親は親。プライドもあるし、自立心もある。
その気持ちを尊重するところから、すべてが始まるんですよね。
②生活の変化を一緒に考える
運転できなくなるというのは、ただの移動手段がなくなるだけではありません。
買い物・通院・趣味の外出…すべてに関わってくる大きな変化です。
だからこそ、家族で一緒に「これからどうするか」を話し合う時間を持つことが大切です。
「週に一回は一緒に買い物に行こうか」「通院はタクシー券が使えるか調べてみるね」など、具体的な選択肢を共有してみてください。
本人が「まだできることがある」と思えるような環境づくりを一緒に考えていけると理想的ですね。
③運転に代わる移動手段を提案する
車に代わる移動手段をどう確保するかは、現実的でとても大事なポイントです。
たとえば:
- 福祉タクシーや乗り合いバス
- 民間の送迎サービス(有料・無料)
- 家族・親戚による定期的な送迎
- 移動販売・宅配サービスの活用
地方に住んでいる方ほど「移動=車頼み」だったりしますが、今は多様なサービスが存在しています。
使い慣れるまでは不安でも、いざ使ってみると「意外と便利だった!」という声も多いです。
無理なく安心できる選択肢を一緒に探してみましょう。
④行政・地域の支援サービスを使う
各自治体では、高齢者の移動や生活を支えるための支援制度が年々充実しています。
たとえば、以下のような制度があります:
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 移動支援サービス | 目的地までの付き添い・送迎 |
| 高齢者向け外出支援制度 | おでかけサポート券や割引制度 |
| 地域包括支援センター | 介護・生活・移動に関する総合相談窓口 |
「そんな制度あったんだ!」という方も多いと思います。
まずは地域の福祉課や包括支援センターに相談して、パンフレットや案内をもらってみてください。
プロの力を借りれば、本人も家族もずっとラクになりますよ。
運転を手放すことは、確かに大きな転機ですが、それを家族でしっかり支えることで、本人の安心感にもつながります。
大切なのは、「もうダメ」ではなく、「これからどうやって楽しく暮らすか」です。
まとめ|認知機能検査で不合格になった場合の対処法
| 検査後の対応ポイント | 詳細リンク |
|---|---|
| 不合格になったら | ①不合格=即失効ではない |
| 診断書や再検査 | ①再検査のチャンスはある |
| 合格への対策 | ①検査内容を事前に理解する |
認知機能検査に不合格となった場合でも、即座に免許が失効するわけではありません。
まずは医師の診断を受けて、認知症でないことが確認されれば、運転技能検査などを経て免許更新の可能性もあります。
また、不合格後でも再受検や診断書の提出で道が開けるケースも多く、必要以上に落ち込む必要はありません。
大切なのは、早めに対処を始めて、冷静に次のステップを踏むことです。
免許を手放すことになっても、行政支援や家族の協力などで、生活を続けていく選択肢はたくさんあります。
正しく知り、備えることで、安心して前を向いて進めますよ。