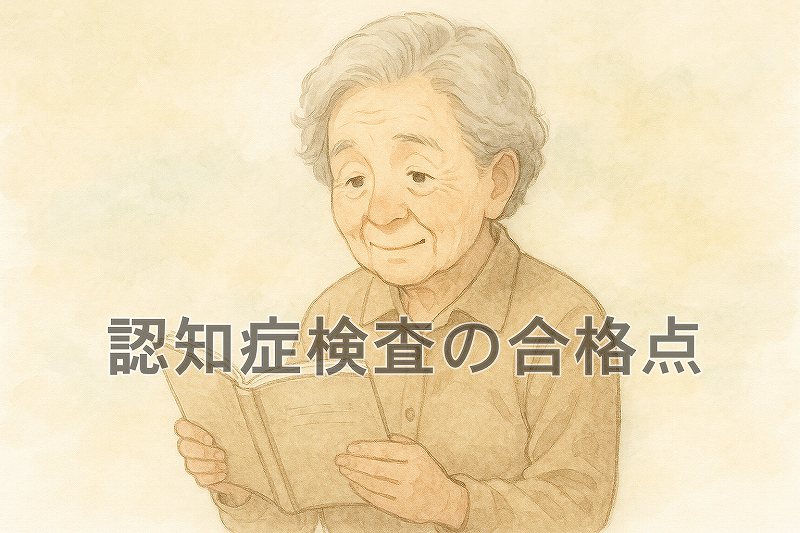認知機能検査の合格点って、何点からOKなの?そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では最新の基準や試験内容、実際に合格するためのコツまでわかりやすく解説します。
認知機能検査の合格ラインは36点上です。
改正された制度によって合格ラインが下がり、以前よりずっと受けやすくなったと言われています。
とはいえ、初めて受ける方にとっては不安も多いですよね。
この記事では、36点以上で合格とされる理由や、試験で出題される内容、失敗しても再チャレンジできる安心制度、そして実体験から学んだ記憶術まで、ぜんぶまとめてお届けします。
この記事を読めば、「自分でも大丈夫!」と思えるようになりますよ。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
認知機能検査の合格点は何点?基本をおさらい
認知機能検査の合格点は何点なのか?基本をおさらいしていきます。
それでは、順番に見ていきましょう!
①2022年の改正で点数区分が変わった
2022年5月13日から、認知機能検査の制度が大きく変わりました。
それまでは「記憶力・判断力が低い」「少し低い」「心配ない」の3区分でしたが、今は2区分に簡素化されました。
現在は「認知症のおそれあり」(不合格)と「認知症のおそれなし」(合格)の2種類に分かれて、より分かりやすい基準となっています。
この改正によって、合格・不合格のラインがよりはっきりし、受検者の負担も軽減されたという声も多いんです。
以前よりも試験内容も簡素化されているので、安心して取り組めますよ~!
②合格と不合格の基準点とは?
認知機能検査の合格点について、正式な「合否」は実は明文化されていないんです。
でも、実務的には「36点以上が合格」「35点以下が不合格」というのが、ほぼ常識的な目安になっています。
満点は100点なので、36点って結構低めのハードルに見えますよね。
この点数をクリアできれば「認知症のおそれなし」の合格と判定されて、免許の更新手続きがスムーズに進みます。
「36点ってホントに大丈夫なの?」って不安な方もいますが、しっかり準備しておけば全然問題なしです!
③36点が合格ラインとされる理由
じゃあ、なぜ36点が合格ラインなのか?その理由を見ていきましょう。
実は、改正前は49点以上が合格ラインだったんです。
でも、制度の見直しによってテスト内容が簡素化されたため、合格ラインも引き下げられました。
この36点というのは、「最低限の記憶力と判断力がある」と判断される基準なんです。
しかも実際の受検者の多くがこの点数を超えているので、「そこまで難しい試験じゃない」っていうのが正直なところですよ!
④100点満点の採点方式の内訳
認知機能検査は100点満点で採点されます。
点数の内訳は以下のようになっています。
| 検査項目 | 配点 |
|---|---|
| 手がかり再生(絵の記憶) | 最大32点 |
| 時間の見当識 | 最大15点 |
| 合計(係数あり) | 100点に換算 |
そしてこの配点に係数がかけられ、最終的なスコアになります。
計算式は「2.499×絵の得点 + 1.336×時間の得点」なんですよ~!
つまり、絵の問題でどれだけ点を取れるかが合格のカギってことですね。
次の章では、認知機能検査の具体的な試験内容をくわしく紹介していきます!
認知機能検査の試験内容をくわしく解説
認知機能検査の試験内容をくわしく解説していきます。
試験の全体像を知っておくことで、合格に近づけますよ!
①イラスト記憶問題の出題形式
イラスト記憶問題は、認知機能検査の中でも最も重要なパートです。
この問題では、まず16枚の絵を4枚1組にして1組ごとに見せられ、それを覚えるところから始まります。
その後、何もヒントのない状態でその絵を言葉で答えさせられます。
1問正解ごとに2点、合計で最大32点がこのセクションに割り当てられています。
さらに、ヒントありで再挑戦するパートもあり、そこで正解すると加点されます(ヒントなし正解の分は除外)。
絵の内容は「にわとり」「バラ」「ペンチ」「ベッド」など、身近なものが多いので、普段からイメージトレーニングをしておくといいですよ!
②時間の見当識テストの内容
このパートでは、「今日は何年?」「何月?」「何日?」「何曜日?」「今は何時何分?」といった質問に答える形式です。
この5問は全問正解(20点)を取ることで、大きなアドバンテージになりますよ~。
試験前にしっかり現在の日時を確認しておくのがコツですね!
③旧制度の「時計描画」は廃止に
以前は、「指定された時間を時計の文字盤に書く」という課題もありました。
これを「時計描画テスト」と呼び、当時は認知機能の視覚的理解力や空間認識を測る手段として使われていました。
しかし、制度改正によりこのテストは廃止され、現在の認知機能検査では実施されていません。
その分、時間や絵に集中することができるので、対策も絞りやすくなっていますよ!
余計な試験がなくなったことで、受検者のストレスも軽減されたと感じる方が多いようです。
④採点に関係しない介入課題とは?
検査中に登場する「介入課題」というのがありますが、これは点数には関係ありません。
たとえば、「たくさんの数字が並んだ表から、指定された数字を斜線で引く」といった作業です。
この課題の目的は、記憶を一時的に遮断して、イラストの記憶力をより正確に測るためなんですね。
つまり、ちょっとした“ひっかけ問題”のようなもので、本来の試験とは無関係なんです。
なので、「採点されない=リラックスしてOK!」という気持ちで臨んでくださいね~。
ここまでで、認知機能検査の試験内容の全体像がつかめたと思います。
次は、実際に合格するためのテクニックについて解説していきます!
認知機能検査に合格するためのコツ5選
認知機能検査に合格するためのコツを5つ紹介していきます。
それでは、具体的なテクニックを見ていきましょう!
①ヒントなしでイラストを覚える方法
合格するには、まずこの「ヒントなし」のパートでできるだけ多く得点することが重要です。
ヒントなしで答えられた問題は、1問あたり5点の高得点がもらえるからです。
おすすめの覚え方は、「ストーリー記憶法」と呼ばれる方法です。
例えば、16枚の絵が「ライオン・たけのこ・フライパン・ものさし…」だったとしましょう。
これらを「ライオンがたけのこを拾って、フライパンで炒めてから、ものさしで測って料理していた」みたいに、ちょっと無理やりでもいいので物語にすると記憶に残りやすいんです。
他にも、「ジャンルごとにグループ化して覚える」方法もあります。動物、鳥、道具など、カテゴリに分けると頭の中で整理しやすくなりますよ!
「イラストは絵で見ると覚えやすい」という方もいると思いますが、言葉だけで記憶する場合は、自分なりのストーリーをつくるのが一番効きます!
②ヒントあり回答で点を稼ぐには
ヒントありのパートでは、ヒントなしで答えられなかったイラストに対して、関連する言葉が提示されます。
ここで「ピンとくる!」という直感が勝負の分かれ目になります。
例えば、「体の一部」と言われて「耳」「目」「親指」「足」などをイメージできると、正解に近づけますよね。
大事なのは、日頃から身近な言葉やモノをしっかりイメージできるように意識すること。
「連想力を鍛えておく」っていうのがポイントですよ〜!
③時間の見当識は全問正解を目指す
このパートでは最大20点が得点できますが、ここを全問正解するのはそんなに難しくありませんね。
試験前に「今日は何年?何月?何日?何曜日?何時?」をしっかりチェックするだけでOK。
当日は、試験会場の時計を確認したり、スマホで時間を把握しておくと安心です。
ここで20点(換算後)取れれば、合格ラインの半分以上を稼げるので、残りは絵の問題でちょっとだけ頑張ればいいんです。
「ここは絶対に落とさない!」という気持ちで、確実に点を取りにいきましょう。
④試験直前のリラックス方法
緊張しすぎて実力が出せない…これってもったいないですよね。
試験前は深呼吸したり、軽くストレッチしたりしてリラックスしましょう。
「落ちたらどうしよう…」と考えるより、「大丈夫、大丈夫」と自分に言い聞かせるほうが効果的ですよ。
緊張が強い人は、好きな音楽を聴いて気持ちを落ち着かせるのもおすすめ。
そして何より、「試験は敵じゃない」って思うことが大事なんです。
⑤高得点を狙うなら事前練習が鍵
本番で焦らないためには、やっぱり練習が一番です。
市販の問題集やネットの模擬問題を活用して、試験の流れに慣れておくと安心ですよ。
特に絵の記憶問題は、何度も練習すればするほどコツがつかめてきます。
時間の見当識の練習は、毎日「今日は何曜日?」「今は何時?」と自問するだけでも違います。
「練習すれば合格できる」っていう安心感が、結果にもつながりますよ〜!
ここで紹介した5つのコツ、ぜひ取り入れてみてくださいね。
次は、不合格になった場合の対応や安心材料についてお伝えします!
認知機能検査に落ちても大丈夫な理由
認知機能検査に落ちても大丈夫な理由を説明していきます。
「落ちたらどうしよう…」と心配しすぎなくても大丈夫ですよ。
①不合格でもすぐに免許停止にはならない
「35点以下=不合格」とされている認知機能検査ですが、実はこの時点で即座に免許停止になるわけではありません。
この点数はあくまで「認知症のおそれあり」と判断されるラインであり、まだ確定ではないんです。
このあと、医師の診断を受けて、本当に認知症かどうかが判定されます。
つまり、この時点では「要検査」という段階なので、落ち込まずに次のステップに進めば大丈夫なんです。
試験を受けて終わりではなく、段階を踏んでちゃんと判断してもらえる仕組みになってるのは安心ですよね~!
②医師の診断で判断が覆るケースもある
不合格になったからといって、「認知症です」と決まるわけではありません。
ここで重要なのが、専門の医師による診断です。
体調不良や緊張など、一時的な理由で点数が下がってしまった場合でも、医師が「認知症ではない」と判断すれば、免許更新は可能なんです。
実際に「検査はうまくいかなかったけど、診断で問題なしとされた」ケースも多くあります。
医師の意見が反映されるって、心強い仕組みですよね。
③高齢者講習で再チャレンジの道がある
もし「認知症ではない」と合格であれば、その後に「2時間の高齢者講習」を受けて、免許更新へと進めます。
この講習では、運転適性検査や講義、実技指導を受けて、安全運転のポイントを再確認する内容になっています。
再チャレンジの道が用意されているからこそ、最初のテストに失敗しても希望はあるんです!
「試験に落ちた=もう終わり」と思わずに、前向きに次のステップへ進んでくださいね。
高齢者講習も、丁寧でやさしい内容になっているのでご安心を!
④体調や環境が悪影響することもある
当日の体調や環境が悪影響して、思わぬ結果になることもあります。
例えば、風邪気味で頭がボーッとしていたとか、寝不足だったとか、そういうちょっとした要因でも記憶力や判断力に影響が出ることがあるんです。
さらに、試験会場の空調が寒すぎたり暑すぎたり、隣の人の咳が気になったりと、集中できない場面もありますよね。
そんなときに実力が出せなかったからといって、自分を責める必要はありません。
「今日は調子が悪かっただけ」と気持ちを切り替えて、必要なら再診や再受検に臨めば大丈夫です!
落ちても、その後のフォロー体制がしっかり整っているので、過剰に心配する必要はありませんよ~。
次は、実体験に基づいたリアルな合格のポイントをご紹介していきます!
不安を解消!実体験に学ぶ合格のポイント
不安を解消!実体験に学ぶ合格のポイントを紹介していきます。
「本当に合格できるの?」という不安に、実体験で応えていきます!
①私が試験を受けた時のエピソード
私自身、認知機能検査をこれまでに2回受けたことがあります。
正直な話、最初は「記憶力に自信がないし、不安だなぁ…」という気持ちでいっぱいでした。
でも実際に受けてみたら、思っていたよりずっと取り組みやすくて、「あれ?これならいけるかも?」と感じました。
特に印象に残っているのは、イラストの記憶問題。ちゃんとコツを押さえれば、確実に点が取れるんです。
しかも2回とも無事に合格できたので、自信にもつながりましたよ〜!
②よく出る絵の種類と覚え方
出題される絵にはある程度パターンがあります。
動物(ライオン・うさぎなど)、文房具(ものさし・万年筆)、野菜(たけのこ・トマト)といった、日常にありふれたものが多いです。
これらを「どうやって覚えるか」が合否を分けるカギになります。
おすすめは、前にも紹介した「ストーリー記憶法」や「ジャンル分け記憶法」。
例えば「ライオンがフライパンでたけのこを炒め、ものさしで長さを測っていた」みたいに、少し笑えるストーリーをつくると記憶に残りやすいですよ!
③気をつけたい試験当日の注意点
当日は「集中できる状態で試験を受ける」ことが何より大事です。
会場に入る前に、トイレを済ませる、水分を少し摂っておく、寒すぎない格好をするなど、体調管理に気を配りましょう。
また、試験中に「今は何時?」と聞かれることがあるので、会場に入る前にしっかり時間をチェックしておくのもポイントです。
緊張しすぎてしまう人は、深呼吸や軽いストレッチでリラックスしてから臨むといいですよ。
「普段通りで大丈夫!」と自分に言い聞かせて、落ち着いて受けてくださいね。
④準備すれば合格できるという安心感
実際に体験して思ったのは、「きちんと準備すれば必ず合格できる」ということです。
イラスト問題も、時間の見当識も、コツを押さえていれば十分対応できます。
練習問題や模擬テストをやっておくだけでも、本番の安心感が全然違います。
そして一番大事なのは、「自分を信じる」こと。
この記事をここまで読んでくれたあなたなら、きっと大丈夫。準備さえすれば、合格できますよ!
まとめ|認知機能検査の合格点を目指すなら安心して準備しよう
認知機能検査は、75歳以上の方が免許更新の際に受ける大切な試験です。
2022年の制度改正で、基準や内容が見直され、36点以上で合格というシンプルな構成になりました。
試験内容は主に「絵の記憶」と「時間の見当識」で構成されています。
この試験に不合格でも、医師の診断や再講習での再チャレンジが可能なため、決して一発勝負ではありません。
しっかり準備をすれば合格は難しくありませんし、実体験を通じて得たコツを押さえることで、ぐっと安心感も増します。
高齢者の方でも無理なく取り組める内容ですので、「認知機能検査って不安…」という気持ちを少しでも減らせたらうれしいです。