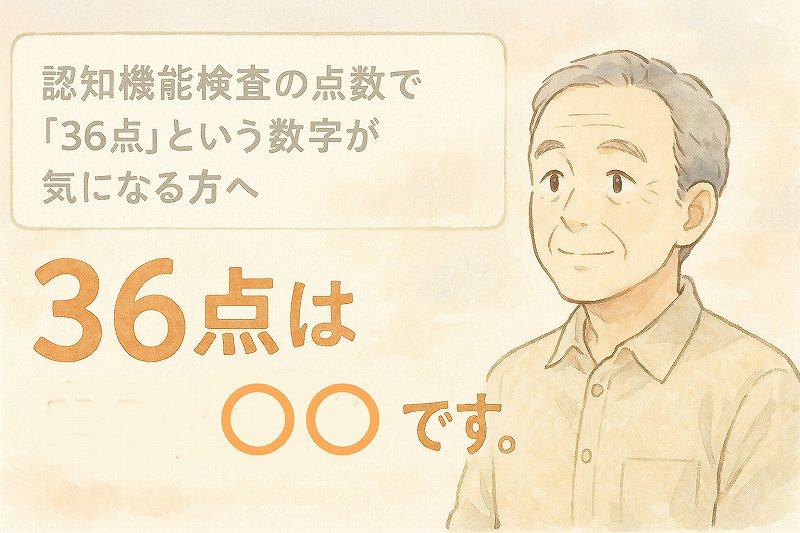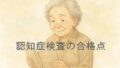認知機能検査の点数で「36点」という数字が気になる方へ。
結論からお伝えすると、36点は合格ラインです。
つまり、36点以上であれば「認知症のおそれなし」と判定され、合格で免許更新は可能です。
ただし、実際の点数は本人に通知されないため、「もしかしてギリギリだったのでは…」と不安になる方もいるかもしれません。
この記事では、認知機能検査の仕組みや採点方法、36点の意味、万が一の再検査への対応、そして安心して検査に臨むための準備法まで、わかりやすく解説しています。
「不安だけど大丈夫かな?」という気持ちに寄り添いながら、必要な情報をぎゅっと詰め込みました。
認知機能検査 点数36点の意味とは?
認知機能検査 点数36点の意味とは、免許更新における合否の分かれ目となる非常に重要な指標です。
それでは、それぞれ詳しく解説していきますね。
①36点以上は合格ライン
認知機能検査において「36点以上」を取れば、警察庁の公式判断では「認知症のおそれがない者」とされ、免許更新が可能になります。
この点数は、100点満点のうちの一部ではありますが、基準としてはかなり重要です。
検査は2種類の項目に分かれていて、その得点を計算式で合算して出た総合点がこの「36点」に相当します。
つまり、「ギリギリでも36点を取れば合格扱い」です。
正直、ヒヤヒヤする点数ではありますが、「合格は合格」なので、更新手続きに進めますよ。
②36点未満は「認知症のおそれあり」
逆に総合点が36点未満(35点以下)だった場合、「認知症のおそれがある者」(不合格)と判断されます。
この場合、すぐに免許を取り上げられるわけではありませんが、医師の診断を受けて、診断書を提出する必要が出てきます。
診断の結果次第では、免許の更新ができない可能性もあります。
また、一度の結果に限らず、再検査を受けて再度点数が出されることもあります。
36点未満という結果は、免許更新において「要注意ゾーン」ですので、慎重な判断が求められますよ。
③判定の根拠は脳科学に基づく
この36点というボーダーラインには、ちゃんとした科学的な根拠があります。
脳科学や認知症の研究データをもとに、「この点数を下回ると日常生活に支障をきたす恐れがある」という判断基準が定められているそうです。
曖昧な基準ではなく、医学的・統計的な研究に基づいたスコアであるため、公的な信頼性も高いです。
とはいえ、日によって調子が変わる人もいるので、個人差を加味して考える必要があります。
「36点」という数字だけで不安になりすぎる必要はないですよ。
④手続き上の分岐点となる重要な数値
36点という点数は、ただのスコアではなく、免許更新の手続き上でも非常に重要な「分岐点」になります。
この点数を超えるかどうかで、更新の流れがガラッと変わるからです。
合格ラインに達していれば、そのまま更新講習を受けるだけでOK。
未満の場合は、医師の診断が必要になり、かなり手続きが煩雑になります。
だからこそ、36点という点数は、免許の行方を左右する大切な数字なんですよ。
認知機能検査の内容と採点方法を詳しく解説
認知機能検査の内容と採点方法を詳しく解説します。
それでは、ひとつずつ説明していきますね。
①手がかり再生とはどんな検査?
手がかり再生とは、記憶力を測定するための検査の一つです。
16枚のイラストが4枚1組で1分ずつ表示され、それを覚えてもらうテストです。
数分後に「覚えていた絵を思い出してください」と言われて、できるだけ多く記憶から取り出す作業になります。
もし思い出せなかった場合でも、「ヒント」を与えられると多くの人がかなり思い出せます。
この“ヒントによる思い出し”も得点に加味されていて、記憶の再生能力全体が評価されますよ。
②時間の見当識テストの内容
時間の見当識とは、「今がいつなのか」を正確に認識できているかを測る検査です。
具体的には、「今日は何年何月何日?」「何曜日?」「今は何時何分?」といった質問に答えます。
このような質問は一見簡単そうに見えますが、実は加齢とともに曖昧になりやすい能力のひとつです。
特に日付や曜日、時間に関しては日常的に確認する習慣がないと忘れがちなんですよね。
でも安心してください。多少の誤差でも、すべてが「アウト」ということにはなりません。
③総合点の計算式とその意味
認知機能検査の点数は、2つの検査の得点を以下の計算式に代入して出します。
| 項目 | 係数 | 内容 |
|---|---|---|
| 手がかり再生(A) | 2.499 | 記憶に関する問題の得点 |
| 時間の見当識(B) | 1.336 | 日付や時間の認識問題の得点 |
| 総合点=2.499×A+1.336×B | ||
つまり、単純な合計ではなく、それぞれの重要度に応じて加重されているんです。
記憶(手がかり再生)のほうが比重が高いことが分かりますね。
記憶に自信がある人は有利かもしれません!
④100点満点中の得点分布はどうなっている?
この検査の満点は100点です。
しかし実際には多くの人が60~80点の間に集中すると言われています。
36点は、その中でもかなり低い位置にあり、「最低限の基準」と考えてよいでしょう。
なので、40点や50点でも、ギリギリ通過の印象になることが多いです。
目安としては、記憶力にやや不安がある人でも60点くらいは取れていることが多い印象です。
検査以外にもチェックされる運転技能の実態
検査以外にもチェックされる運転技能の実態について解説します。
では、実際にどんなチェックがあるのか見ていきましょう。
①段差乗り越え・幅寄せのチェック
運転技能の実技検査では、たとえば「段差をゆっくり乗り越える」などの課題があります。
これは、高齢になると視認性や足の動きに衰えが出やすく、慎重に越えられるかを確認するためです。
このような課題を通じて、細やかなブレーキ操作や車幅感覚などが見られます。
教習所ではこれらのテストを丁寧に行っており、指導員が横についてフォローしてくれるので安心ですよ。
②アクセルとブレーキの踏み間違い対策
高齢ドライバーで特に多いのが、アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故です。
そのため、実車テストでは「急発進しないか」「ブレーキのタイミングが適切か」が重点的に見られます。
急ブレーキが必要な状況で反応が遅れたり、反射的にアクセルを踏んでしまうような場面は危険と判断されることもあります。
特に街中や駐車場では、ペダル操作の誤りが命取りになる可能性があるので、この検査はとても重要です。
最近では、実技指導の中で踏み間違いの癖を指摘してくれるところも増えてきました。
③個人差と体調の影響
実車検査で顕著なのは、体調や個人差による「出来のバラつき」です。
普段の運転は問題なくても、緊張や睡眠不足などで本番の出来が悪くなる人もいます。
逆に、普段やや心配でも、緊張感を持って運転したら安定していたという例もあります。
検査官や指導員もこの点をよく理解していて、「その人らしい運転」ができているかを見てくれています。
だからこそ、検査当日の体調管理はとても重要ですよ!
④セフモによる運転技術の可視化
「セフモ」という最新システムの導入も始まっています。
これは、車載カメラとGPSを活用し、運転中の行動をすべてデータ化・動画化する仕組みです。
「停止線を越えていないか?」「センターラインをまたいでいないか?」などが数値と映像で分かります。
自分の運転を客観的に振り返ることができるため、「次の更新に向けた自己チェック」に役立つツールです。
これから全国に広がっていく可能性もある注目の仕組みですね。
認知機能検査に不安がある方への対策と準備法
認知機能検査に不安がある方への対策と準備法を紹介します。
検査当日を安心して迎えるために、できる準備をしておきましょう。
①検査前にやっておきたいこと
認知機能検査は「普段の認知力」を見るためのものですが、少し準備をしておくだけでも結果が安定します。
まずは前日によく眠ること。睡眠不足は記憶力や判断力に大きく影響します。
また、当日の朝食はしっかりと摂りましょう。血糖値が安定していると、脳の働きも良くなります。
検査時間に余裕をもって会場に向かい、緊張しすぎないことも大切です。
「深呼吸してリラックスして臨む」ことを意識してみてくださいね。
②記憶力・注意力トレーニングの方法
日常生活の中でできる記憶トレーニングはたくさんあります。
たとえば、新聞の見出しを声に出して読んで覚える、買い物メモを使わずに買い物に挑戦してみる、といった方法があります。
また、絵や写真を見て、5分後に何があったかを思い出す練習も効果的です。
注意力に関しては、数字探しや間違い探しのようなゲーム感覚のトレーニングがおすすめ。
スマホアプリや高齢者向け脳トレ本も活用すると、楽しく継続できますよ。
③生活習慣で意識すべきポイント
認知機能は、生活習慣と密接につながっています。
適度な運動、バランスの良い食事、会話の多い生活が、脳の活性化に役立ちます。
特にウォーキングは「脳を育てる運動」として有名です。
また、毎日カレンダーを見る習慣や、日記をつけることも「時間の見当識」を鍛えるのにぴったりです。
生活の中に「ちょっと頭を使う場面」を意識的に増やすだけでも、大きな違いが出てきますよ。
④家族がサポートできること
受検者本人だけでなく、家族ができるサポートもたくさんあります。
まずは「無理に受けさせる」のではなく、「応援している」というスタンスを取ることが大切です。
一緒に日付確認の練習をしたり、写真を見て思い出すゲームをするのもいいですね。
検査前の緊張を和らげる声かけや、検査後のフォローも大切です。
もし結果に不安がある場合は、早めにかかりつけ医と相談するのも一つの手ですよ。
まとめ|認知機能検査 点数36点が意味するもの
認知機能検査における「36点」という点数は、運転免許更新のための合格・不合格を分ける非常に重要な基準です。
36点以上であれば「認知症のおそれなし」として合格扱いとなり、免許更新に進むことができます。
しかし、受検者本人には点数が通知されないため、検査後に不安を感じる方も少なくありません。
そういった方のために、この記事では検査の具体的な内容から実技の様子、日常でできる対策まで幅広く解説しました。
検査を安心して受けたい方、またご家族が気にされている方にとって、少しでも役立つ情報となっていれば幸いです。