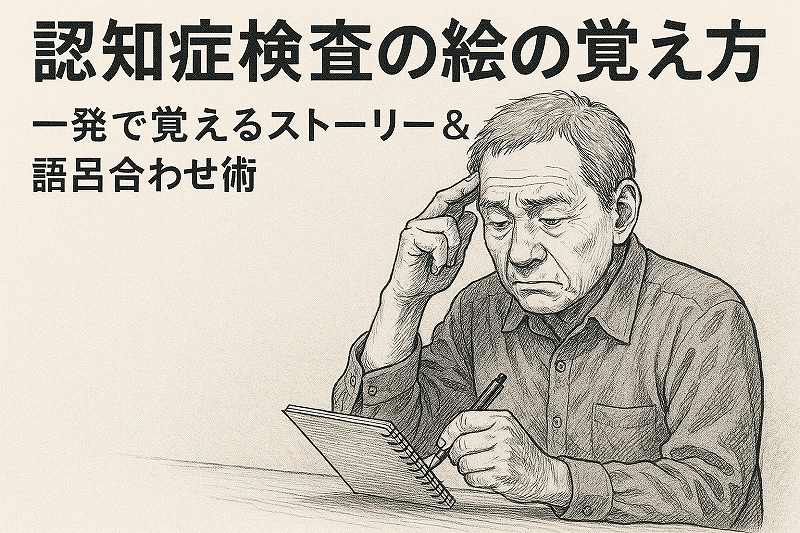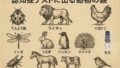認知症検査に向けて「絵の覚え方」を探しているあなたへ。
この記事では、「認知症 検査 絵の覚え方」というテーマで、パターン別に効果的な記憶法を詳しくご紹介しています。
ストーリー記憶法や語呂合わせ、五感を活かした覚え方など、試験が不安な方にもすぐ実践できるコツが満載!
この記事を読むことで、検査への不安がスッと軽くなり、「これならできる!」と自信を持てるはずです。
ぜひ、最後まで読んで、あなたにピッタリの覚え方を見つけてくださいね!
認知症検査で絵を覚えるコツ7選
認知症検査で絵を覚えるコツ7選について解説していきます。
それでは、順番に見ていきましょう!
①ストーリーでつなげる
絵を単体で覚えようとすると、どうしても忘れやすくなります。
そこでおすすめなのが、ストーリーでつなげる方法です。
例えば「大砲」「耳」「ラジオ」と並んでいたら、「大砲の音で耳が痛くなり、ラジオで癒された」という流れを作ってみましょう。
物語を作ると、自然と次の絵が連想できるので、かなり記憶しやすくなりますよ!
想像力を働かせて、自分なりのストーリーを考えてみてくださいね。
②語呂合わせを活用する
語呂合わせもめちゃくちゃ効果的な覚え方です!
たとえば「トンボ」「うさぎ」「トマト」なら、「トンウサトマ」とリズムよく覚えていきます。
短く、口に出しやすい語呂を作ると、何度も唱えるだけで頭に入ってきます。
「ちょっとダサいかな?」くらいの語呂でも大丈夫。覚えやすさ優先でいきましょう!
語呂を作るときは、口に出してみるのがコツですよ~。
③五感をフル活用して覚える
視覚だけじゃなく、聴覚や触覚までイメージすると、記憶力はぐっとアップします!
例えば、ラジオなら「ザザッ…」という雑音の音を思い浮かべたり。
トウモロコシなら、パリッとした手触りや、甘い香りをイメージしてみたり。
五感をフルに使うことで、脳のいろんな部分が活性化されて、覚えやすくなるんです。
どんどんリアルに想像してみてくださいね。
④情景をイメージする
情景を頭の中に描くと、より一層記憶に残ります。
例えば「ライオン」と「スカート」なら、サバンナでスカートをはいた観光客を想像する、みたいな感じです!
突飛なイメージの方が、逆に覚えやすくなるので、自由に想像しちゃってOK。
普通じゃないシーンのほうが、あとから思い出すときに役立つことも多いですよ!
面白い情景を作って楽しみながら覚えましょう~!
⑤リズムで覚える
リズムに乗せて覚えると、記憶の定着がグッと良くなります。
たとえば、歌のサビに合わせて単語を当てはめるだけでも効果あり。
童謡とか、知ってる曲に乗せるとさらに覚えやすいです。
ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、リズムに乗るだけで不思議と忘れにくくなりますよ!
ノリノリで覚えちゃいましょう~♪
⑥声に出して反復する
声に出すのもめちゃくちゃ大事なポイント。
脳は「自分の声」で聞いた情報をより強く記憶する性質があります。
朝起きたとき、寝る前、スキマ時間に、ボソボソでもいいので唱えてみましょう。
ちょっとずつ頭に刷り込まれていきます。
音読するクセ、ぜひつけてみてくださいね~!
⑦グループ分けして整理する
たくさんの絵を一気に覚えようとすると、どうしても混乱しますよね。
そんなときは、4~5個ずつ小分けにして、グループごとに整理してみましょう。
例えば「乗り物グループ」「食べ物グループ」みたいに分けるとスッキリ覚えられます。
カテゴリごとに頭の中で引き出しを作るイメージです。
整理してから覚えると、記憶も取り出しやすくなりますよ!
認知症検査の絵パターンAを覚える方法
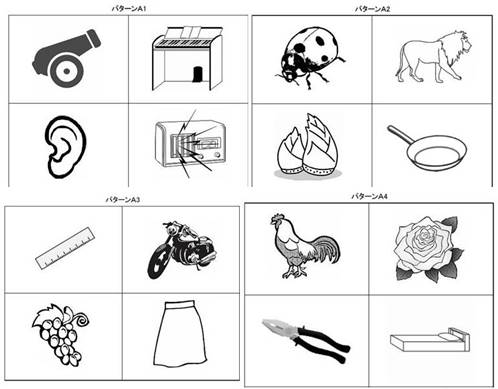
- 大砲(戦いの武器)
- オルガン(楽器)
- 耳(体の一部)
- ラジオ(電気製品)
- てんとう虫(昆虫)
- ライオン(動物)
- たけのこ(野菜)
- フライパン(台所用品)
- ものさし(文房具)
- オートバイ(乗り物)
- ぶどう(果物)
- スカート(衣類)
- にわとり(鳥)
- バラ(花)
- ペンチ(大工道具)
- ベッド(家具)
認知症検査の絵パターンAを覚える方法について解説していきます。
それでは、順番にチェックしていきましょう!
①日常生活に例える
パターンAに登場する絵を、日常生活の一コマに当てはめる方法はとても効果的です。
例えば、「大砲」「オルガン」「耳」「ラジオ」なら、
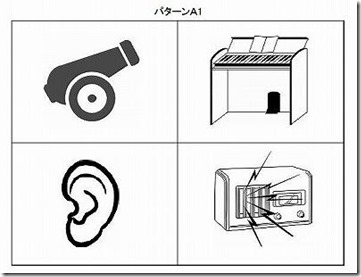
「朝、大砲の音で目覚めて、隣からオルガンの音が聞こえ、耳を澄ませたらラジオからニュースが流れてきた」という感じに!
身近な体験に似たシチュエーションにすると、すっと頭に入ってきます。
イメージできるほど記憶も強くなるので、自分の日常とリンクさせて覚えてみてくださいね!
②連想ストーリーを作る
イラストを一つずつバラバラに覚えるのではなく、つなげてストーリーを作る方法がめちゃくちゃおすすめです!
例えば、「てんとう虫」「ライオン」「たけのこ」「フライパン」なら、
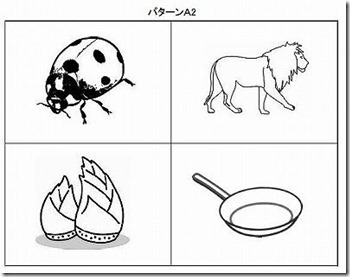
「庭でてんとう虫を見つけたら、ライオンの置物のそばで、たけのこを拾って、フライパンで炒めた」というストーリーにする感じです!
バラバラな絵でも、意味づけして流れを作ると自然に覚えられます。
自分だけの楽しいストーリーを作って、楽しく記憶していきましょう~!
③リスト化して目で確認する
パターンAの16個の絵を、まずはリストにして見える化しましょう。
視覚的に一覧にすることで、「これがまだ覚えられてないな」とか、「このグループはもうバッチリ!」みたいに進捗管理ができるようになります。
実際にメモ帳やノートにリストを作って、できればチェックボックスもつけると、達成感も得られてモチベアップ!
「目で確認する」って、意外と記憶にめちゃくちゃ効きますよ!
地味だけど超効果的なので、ぜひやってみてくださいね!
認知症検査の絵パターンBを覚えるコツ
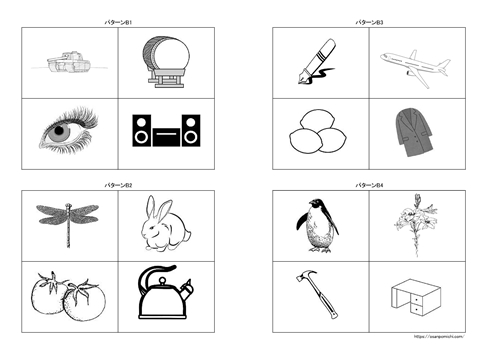
| ヒント | パターンB | |
| 1 | 戦いの武器 | 戦車 |
| 2 | 楽器 | 太鼓 |
| 3 | 体の一部 | 目 |
| 4 | 電気製品 | ステレオ |
| 5 | 昆虫 | トンボ |
| 6 | 動物 | うさぎ |
| 7 | 野菜 | トマト |
| 8 | 台所用品 | やかん |
| 9 | 文房具 | 万年筆 |
| 10 | 乗り物 | 飛行機 |
| 11 | 果物 | レモン |
| 12 | 衣類 | コート |
| 13 | 鳥 | ペンギン |
| 14 | 花 | 百合 |
| 15 | 大工道具 | カナヅチ |
| 16 | 家具 | 机 |
認知症検査の絵パターンBを覚えるコツについて解説していきます。
それでは、順番にチェックしていきましょう!
①語呂合わせでリズムよく覚える
パターンBは、語呂合わせを使うとめちゃくちゃ覚えやすくなります!
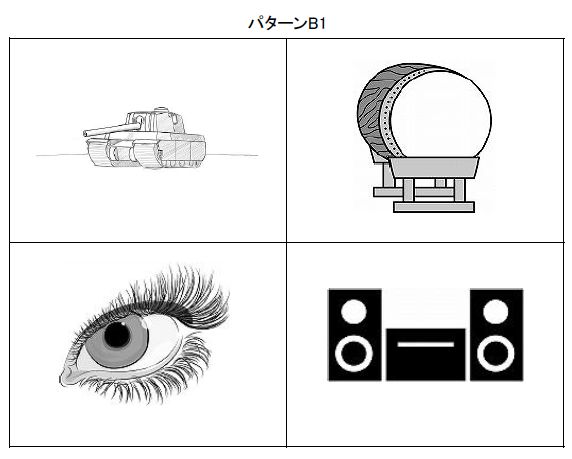
例えば「戦車」「太鼓」「目」「ステレオ」なら、「せんたいためすて」とかリズミカルに並べて覚える感じです。
無理やりでもいいので、音の響きが気持ちいい並びを作ると、スムーズに口から出てくるようになります。
リズムに乗せると、脳も「楽しい!」と感じるので、記憶の定着がめっちゃよくなりますよ~!
オリジナルの語呂合わせをどんどん作ってみてくださいね!
②シチュエーションを設定する
語呂だけだと物足りないな~と感じたら、シチュエーション設定をプラスしてみましょう!
例えば、戦車が進軍している森で太鼓が鳴り響き、兵士たちが目をこらして遠くのステレオ音を聞く…みたいなストーリーです!
場所や状況をしっかり決めると、絵同士のつながりが強くなるので、思い出すときもスムーズになります。
森でも、キャンプ場でも、宇宙でもOK!想像力全開で自由にシーンを作ってくださいね!
楽しいシチュエーションを作れば作るほど、覚えるのも楽になりますよ!
③声に出して暗唱する
最後は王道ですが、「声に出して何度も唱える」です!
やっぱり脳って、自分の声を聞くと覚えやすいんですよね。
最初はぎこちなくてもいいので、何度も何度も声に出して読むだけで、自然に体にしみ込んでいきます。
できれば、朝と夜の2回読む習慣をつけると最高です!
小声でもいいので、できるだけたくさん口に出して覚えていきましょう~!
認知症検査の絵パターンCを記憶する方法
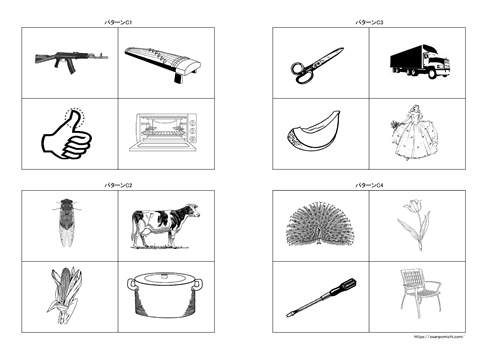
| ヒント | パターンC | |
| 1 | 戦いの武器 | 機関銃 |
| 2 | 楽器 | 琴 |
| 3 | 体の一部 | 親指 |
| 4 | 電気製品 | 電子レンジ |
| 5 | 昆虫 | せみ |
| 6 | 動物 | 牛 |
| 7 | 野菜 | トウモロコシ |
| 8 | 台所用品 | ナベ |
| 9 | 文房具 | ハサミ |
| 10 | 乗り物 | トラック |
| 11 | 果物 | メロン |
| 12 | 衣類 | ドレス |
| 13 | 鳥 | クジャク |
| 14 | 花 | チューリップ |
| 15 | 大工道具 | ドライバー |
| 16 | 家具 | 椅子 |
認知症検査の絵パターンCを記憶する方法について解説していきます。
それでは、順番に詳しく見ていきましょう!
①視覚的にストーリー化する
パターンCのイラストは、「視覚的にストーリー化」するのがめちゃくちゃ効果的です!
例えば、「機関銃」「琴」「親指」「電子レンジ」という順番なら、
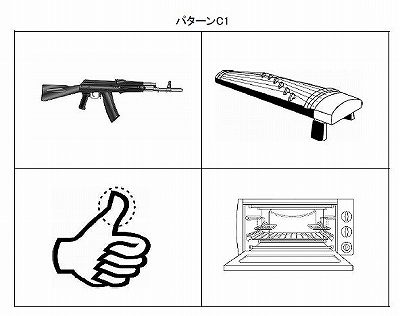
「機関銃の音に驚いて廊下に走り、琴の音色が聞こえ、親指を突き指して電子レンジで温めた」みたいに映像を思い浮かべてみましょう。
頭の中でまるで映画を再生するように、場面をつないでいくとすごく覚えやすいですよ!
大げさな設定でも、変なシチュエーションでも全然OK!とにかく映像をイメージすることがポイントです!
②イメージを膨らませる
覚えたいイラスト一つ一つに、イメージを膨らませるとさらに記憶に残りやすくなります。
例えば「セミ」だったら、ミンミン鳴く音や、真夏の暑さ、木にとまる姿まで想像する感じです!
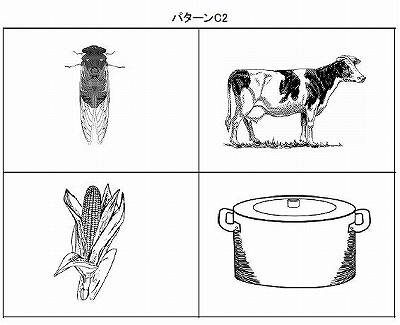
「牛」なら、もこもこした毛並み、のんびりした表情、草をもぐもぐ食べる様子を想像してみましょう。
イメージを広げれば広げるほど、脳に定着しやすくなります!
ちょっとオーバーなくらい膨らませて想像してOKですよ~!
③五感を意識して覚える
視覚だけじゃなく、五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)をフルに使って覚えると超強力です!
例えば「ドライバー」なら、金属のひんやりした感触や、ネジを締めるときの「キュッ」という音をイメージします。
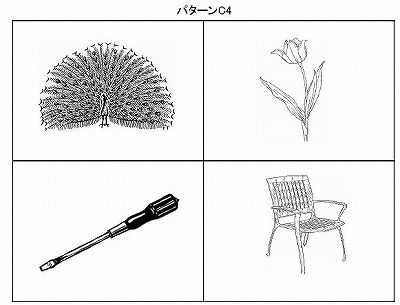
「メロン」なら、甘~い香り、ジュワッと広がる味わいを想像すると◎。
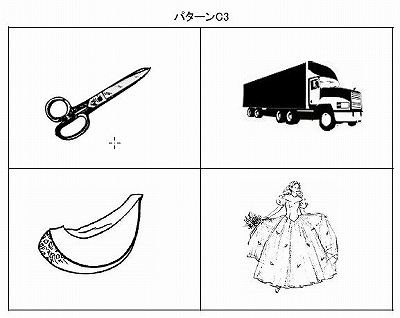
五感で感じた情報は、脳に深く刻まれるので、普通に覚えるよりずっと記憶に残りやすくなります。
ぜひ、五感フル活用でチャレンジしてみてくださいね!
認知症検査の絵パターンDをスムーズに覚えるには
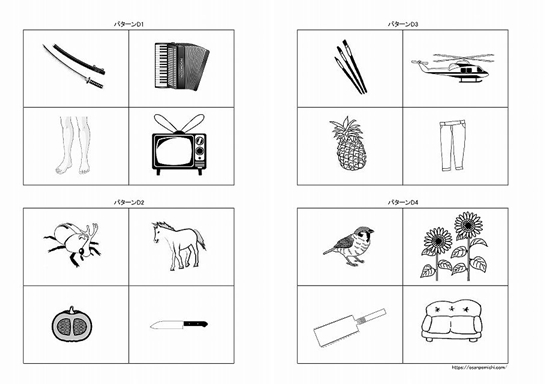
| ヒント | パターンC | |
| 1 | 戦いの武器 | 刀 |
| 2 | 楽器 | アコーディオン |
| 3 | 体の一部 | 足 |
| 4 | 電気製品 | テレビ |
| 5 | 昆虫 | カブトムシ |
| 6 | 動物 | 馬 |
| 7 | 野菜 | カボチャ |
| 8 | 台所用品 | 包丁 |
| 9 | 文房具 | 筆 |
| 10 | 乗り物 | ヘリコプター |
| 11 | 果物 | パイナップル |
| 12 | 衣類 | ズボン |
| 13 | 鳥 | スズメ |
| 14 | 花 | ひまわり |
| 15 | 大工道具 | ノコギリ |
| 16 | 家具 | ソファー |
認知症検査の絵パターンDをスムーズに覚えるにはについて解説していきます。
順番に解説していきますね!
①日常シーンに落とし込む
パターンDは、身近な日常シーンに落とし込むことでグッと覚えやすくなります!
たとえば、「刀」「アコーディオン」「足」「テレビ」という並びなら、
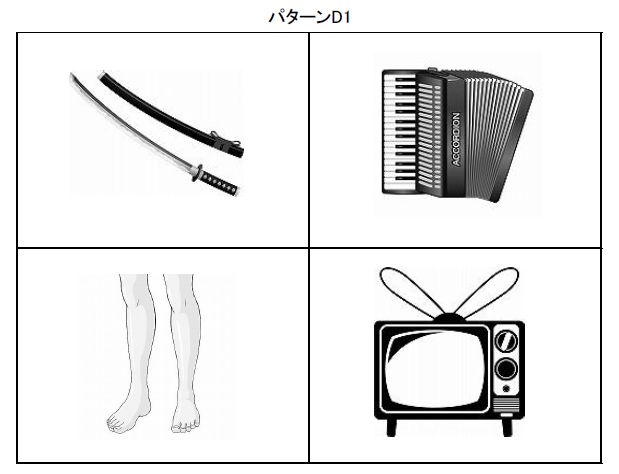
「祖父が刀を磨きながらアコーディオンを弾いている。孫が裸足で走り回り、その間テレビでは昆虫番組が流れている」といった具合です。
自然な日常の流れに絵を溶け込ませることで、スムーズに記憶できるようになります。
自分の生活に当てはめたり、家族とのシーンを想像したりして、楽しく覚えてくださいね!
②まとめてセットで覚える
16個全部を一気に覚えようとするとパンクしそうですが、安心してください。
コツは「まとめてセットで覚える」ことです!
例えば「刀」「アコーディオン」「足」「テレビ」までをひとまとめにして、1つのエピソードにします。
次に「カブトムシ」「馬」「カボチャ」「包丁」でまた一つのシーンを作る、という感じですね。
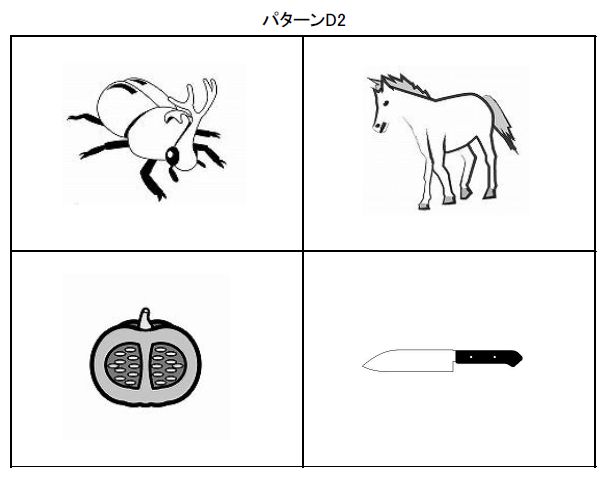
小さなかたまりをいくつも覚えていくと、最後には自然に全体がつながっていきますよ!
③身近なモノと結びつける
パターンDに出てくる絵は、身近なモノが多いので、どんどん自分の体験に結びつけちゃいましょう!
例えば、「ひまわり」なら、夏に見たあのひまわり畑を思い出して。
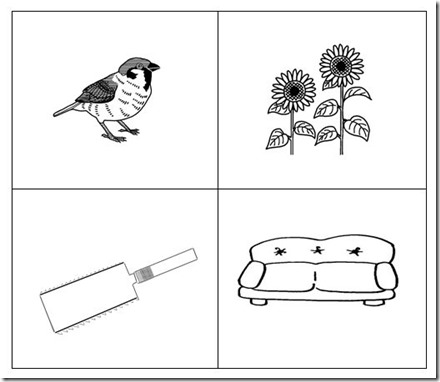
「ズボン」なら、お気に入りのズボンを履いた日のことをイメージして。
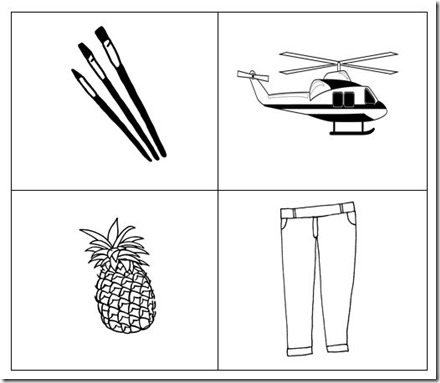
身近なモノにリンクさせることで、「これ知ってる!」という安心感が生まれ、記憶の定着率が一気にアップします!
どんどん自分のエピソードとリンクさせて覚えていきましょう~!
まとめ|認知症検査の絵を覚えるコツを身につけて安心しよう
認知症検査に向けて、絵を覚えるのが不安に感じる方も多いと思います。
でも、コツをつかめば、覚える作業もずっと楽しくなりますよ!
今回ご紹介したストーリー化や語呂合わせ、五感を使ったイメージ法を取り入れて、焦らず一つずつ取り組んでいきましょう。
早めに準備を始めることで、当日も落ち着いて検査に臨めるようになります。