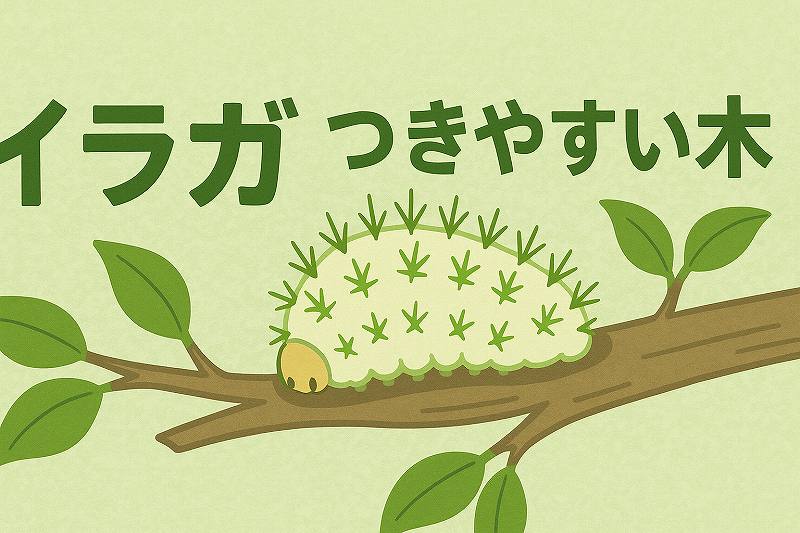イラガはカキやサクラ、キンモクセイなど、多くの庭木に付きやすい有毒な毛虫です。
刺されると激しい痛みや炎症を引き起こし、場合によってはアナフィラキシーショックの危険もあります。
しかも雑食性で「どんな木にも発生する可能性がある」ため、庭木を育てている家庭では常に注意が必要です。
この記事では、イラガが付きやすい木の種類や特徴、発生を見分けるポイント、駆除と予防の方法まで詳しく解説します。
一覧表も使って比較できるので、自分の庭木が被害を受けやすいかどうか、すぐに判断できます。
正しい知識と早めの対応で、庭木と家族の安全をしっかり守りましょう。
イラガ つきやすい木とその特徴を徹底解説

イラガ つきやすい木とその特徴を徹底解説します。
それでは、具体的に見ていきましょう。
①カキ

カキの木はイラガの被害が特に多い代表的な樹種です。
夏から秋にかけての葉は柔らかく栄養が豊富で、幼虫が集団で発生しやすくなります。
被害が進むと葉の表面が白くかすれたり、葉脈だけを残して葉肉が食べ尽くされることもあります。
また、枝や幹に繭が付着して越冬するため、冬場でも発見のチャンスがあります。
特に家庭菜園や庭でカキを育てている場合は、収穫シーズン前後に注意が必要です。
②サクラ・ウメ(バラ科)

サクラやウメなどのバラ科の木もイラガにとって魅力的な食糧源です。
春に花を楽しむ樹木ですが、夏以降の葉が柔らかい時期に食害を受けやすくなります。
特に観賞用のサクラは街路樹や公園にも多く植えられており、近くにあると庭木にも被害が波及することがあります。
ウメは果樹として育てられることも多く、果実や葉に被害が及ぶと樹勢が弱るため注意が必要です。
葉裏や枝の分かれ目を観察して、卵や幼虫を早期発見しましょう。
③モミジ(カエデ科)
モミジやカエデ科の木は葉の質感が柔らかく、イラガ幼虫が好んで食害します。
夏から秋にかけて葉色が変わり始める時期でも被害が出やすく、観賞価値を損ないます。
特に庭や公園に植えられている場合は、人通りが多い場所での接触事故にも注意が必要です。
幼虫は葉の表面だけでなく裏側にも潜むため、両面をしっかり観察することがポイントです。
落葉後も枝に繭が残ることがあるので、冬の剪定時に併せて駆除すると効果的です。
④ヤナギ
ヤナギは湿地や水辺に多く生える木で、柔らかい葉を持つためイラガの発生が見られます。
特に樹勢が旺盛で枝葉が密になると、幼虫が隠れやすくなります。
水辺は風通しが悪く湿度が高いため、害虫が繁殖しやすい環境になります。
葉先や枝の先端部を重点的に確認し、白くかすれた葉を見つけたら幼虫の存在を疑いましょう。
庭にヤナギを植える場合は、定期的な剪定で風通しを確保することが重要です。
⑤キンモクセイ・ヒイラギモクセイ(モクセイ科)
香りの良い花で人気のキンモクセイやヒイラギモクセイも、イラガが好む樹木のひとつです。
葉が厚めで丈夫そうに見えますが、柔らかい新芽は特に食害されやすい傾向があります。
被害を受けると花付きや香りにも影響するため、庭の観賞価値が下がってしまいます。
剪定や花後の手入れ時に、必ず葉裏や枝の状態をチェックして早期対応を行いましょう。
繭が枝に固く付着している場合は、枝ごと切り取り密閉処分するのが安全です。
⑥シマトネリコ・ギンヨウアカシア・オリーブ
これらの木は害虫が付きにくいとされますが、イラガの発生例は珍しくありません。
特に暖かい地域や日当たりの良い場所では発生リスクが上がります。
油断していると発見が遅れ、気づいたときには葉がスカスカになることもあります。
「イラガが付かない木はない」という意識で、定期的な観察を欠かさないことが大切です。
新しく植える際も、苗木や枝に繭が付着していないか事前にチェックしましょう。
イラガ発生の見分け方5つのポイント
イラガ発生の見分け方5つのポイントを解説します。
それでは、順番に詳しく見ていきましょう。
①葉の白いかすれ
イラガ幼虫の初期被害は、葉の表面が白っぽくかすれたように見えるのが特徴です。
これは孵化直後の幼虫が葉の汁を吸う際に、葉の表面組織を壊すために起こります。
特に夏から初秋にかけて、この症状が出た葉は要注意です。
被害が広がる前に、その葉ごと切り取って処分すると効果的です。
葉の色が変わっただけだからと油断すると、数日で集団食害に発展する可能性があります。
②葉脈を残した食害

成長した幼虫は葉脈を残して葉肉を食べるため、葉がレース状になります。
これは進行被害のサインで、すでに複数の幼虫が葉に分散している状態です。
この段階になると手作業での駆除は難しく、木全体への薬剤散布が必要です。
特に上部や裏側の葉もチェックし、被害が見えない部分にも注意してください。
葉脈だけが残った葉を見つけたら、すぐに駆除の準備をしましょう。
③幼虫の群生

孵化直後の幼虫は群れを作り、一つの葉や枝に集中して集まります。
この時期に発見できれば、被害を最小限に抑えられるチャンスです。
幼虫は明るい黄緑色や褐色で、体に有毒な棘があり、ウミウシのような形をしています。
絶対に素手で触らず、割り箸やピンセットを使って葉ごと処分します。
集団での発生は見つけやすい反面、放置すると一気に広範囲に広がる危険があります。
④枝についた繭

イラガの繭は冬場に見つけやすく、枝に固く付着しています。
茶色やうずらの卵のような白い斑模様のある卵型で、しっかり固定されているのが特徴です。
繭の中にも毒がある種類がいるため、触る際には厚手の手袋を必ず着用してください。
駆除はヘラでこそぎ落とすか、枝ごと切り取り袋に密閉して処分します。
繭を残すと翌年の発生源になるため、冬の間に見つけて除去するのが理想です。
⑤冬場の卵や繭の発見
冬期は葉が落ちて枝が見やすくなるため、卵や繭の確認がしやすくなります。
卵は小さく枝に密着して産み付けられ、繭と同様に翌年の被害を引き起こします。
特に剪定作業の際は、卵や繭を見逃さないよう丁寧に観察しましょう。
卵や繭を見つけた場合は、必ずビニール袋に入れて密封し、廃棄します。
この冬場のチェックが、翌年のイラガ被害を減らす最も確実な方法のひとつです。
イラガ駆除の正しい手順4ステップ
イラガ駆除の正しい手順4ステップを解説します。
それでは安全で効果的な駆除方法を詳しく見ていきましょう。
①防護服と手袋を着用
イラガ駆除の基本は「絶対に素手で触らないこと」です。
幼虫や繭には毒棘があり、触れると激しい痛みや炎症を引き起こします。
作業時は長袖・長ズボン・厚手の手袋を着用し、可能ならばゴーグルやマスクも装着しましょう。
枝を揺らすと幼虫が落下して肌に触れる危険があるため、下にブルーシートを敷くのも有効です。
安全装備を整えることが、作業をスムーズに進める第一歩です。
②幼虫の捕殺

幼虫は必ず道具を使って捕殺します。
割り箸やピンセットでつかみ、そのままバケツの中で処理する方法が安全です。
群生している場合は、被害葉や小枝ごと切り取って処分します。
この際、ビニール袋に入れて密封し、ゴミとして廃棄するのが基本です。
早期発見できればこの手順でほとんどの被害を防げます。
③殺虫スプレーや熱湯で駆除
広範囲に幼虫が広がっている場合は殺虫スプレーを使用します。
市販の「ベニカJスプレー」や噴射力の強いジェットタイプが便利です。
高所の枝にいる場合は脚立を使わず、長距離噴射できる製品を選びましょう。
薬剤を使いたくない場合は熱湯を直接かける方法もありますが、火傷に十分注意が必要です。
どちらの場合も、作業後はしっかり手洗いと衣類の洗濯を行ってください。
④枝ごと切り取って処分
繭や卵が枝に固着している場合は、枝ごと切り取るのが確実です。
ハサミやノコギリで切り落とし、すぐに袋に入れて密封します。
繭の中には毒を持つ種類もいるため、処理は慎重に行いましょう。
この作業は冬場の剪定と合わせて行うと効率的で、翌年の発生を抑制できます。
不要な枝を整理することで風通しが良くなり、害虫の発生自体も減少します。
イラガ予防で効果的な方法5選
イラガ予防で効果的な方法5選を解説します。
では、発生を未然に防ぐための具体的な方法を見ていきましょう。
①定期的な薬剤散布
イラガは発生時期が長く、一度駆除しても再び発生することがあります。
そのため、発生期の7月から11月にかけては定期的な薬剤散布が有効です。
「スミチオン乳剤」など希釈タイプの殺虫剤を使うと、広範囲の予防が可能です。
ただし、産卵や孵化のタイミングによっては効果が限定的になるため、併せて目視確認も欠かせません。
薬剤散布は風の弱い日を選び、周囲の植物やペットへの影響にも配慮しましょう。
②庭木の剪定で見通しを良くする
枝葉が混み合った庭木は、卵や幼虫が見つかりにくくなります。
風通しも悪くなり、害虫にとって居心地の良い環境になってしまいます。
定期的に剪定して内部まで日光と風が届くようにすることで、発生リスクを下げられます。
特に梅雨明けや夏前に軽く剪定しておくと、発生初期の発見がしやすくなります。
剪定作業後は切り落とした枝葉をそのまま放置せず、速やかに処分してください。
③繭の早期除去
冬場に発見できる繭は翌年の発生源になります。
枝に固着しているため、ヘラでこそぎ落とすか、枝ごと切り取るのが効果的です。
繭は外見上は硬く乾燥して見えますが、中の個体は春に羽化するまで生きています。
繭ごとビニール袋に入れて密封し、燃えるゴミとして処分しましょう。
冬の剪定と同時に繭を探す習慣をつけることで、翌年の発生を大幅に減らせます。
④植え付け前のチェック
新しい庭木を植える際には、枝や幹に繭や卵が付いていないか必ず確認します。
苗木の段階で既にイラガが付着していると、そのまま庭に持ち込んでしまいます。
特にホームセンターや園芸店で購入した苗は、よく観察してから持ち帰りましょう。
可能であれば植え付け前に薬剤を散布し、持ち込みリスクを減らすこともおすすめです。
「どんな木にも付く」という意識を持ち、慎重にチェックすることが大切です。
⑤浸透性殺虫剤の活用
浸透性殺虫剤は、木全体に有効成分が行き渡るため、長期的な予防に役立ちます。
「オルトランDX」のような製品を根元に撒くと、葉を食べた害虫にも効果があります。
即効性はないものの、発生を抑える補助的な手段として有効です。
特に毎年同じ木に発生する場合や、薬剤散布が難しい高木に適しています。
春先や初夏に撒いておくと、発生期に入ったときの被害を軽減できます。
庭木と家族を守るための注意点
庭木と家族を守るための注意点を解説します。
では、イラガ対策を行う上で特に大切な安全面のポイントを見ていきましょう。
①子どもやペットの安全確保
イラガは庭の低い位置や手の届く高さの葉にも付くため、子どもやペットが触れる危険があります。
刺されると強い痛みや炎症を引き起こし、場合によっては病院での治療が必要になります。
庭で遊ぶ際は、必ず大人が付き添い、害虫の発生がないか事前に確認しましょう。
発生が確認された場合は、そのエリアに近づけないようにすることが大切です。
安全を守るためには、庭全体の定期的な点検が欠かせません。
②作業時の防護
イラガ駆除や庭木の手入れをする際は、防護服や厚手の手袋を必ず着用します。
毒棘は衣服の上からでも刺さることがあるため、厚手の素材を選びましょう。
さらにゴーグルやマスクを装着すれば、落下した幼虫や飛び散った棘から目や口を守れます。
庭作業は早朝や夕方など涼しい時間帯に行うと、安全かつ集中して作業できます。
作業後は衣服をすぐに洗濯し、体をしっかり洗い流してください。
③発見後の迅速な対応
イラガは短期間で成長し、被害を急速に拡大させます。
発見したらその日のうちに駆除することが、被害を最小限に抑えるポイントです。
薬剤散布や捕殺の準備を常に整えておくと、迅速に対応できます。
特に夏から初秋は発生のピークとなるため、見回りの頻度を上げましょう。
一度発生した木は翌年も被害を受けやすいため、予防策も併せて行うことが重要です。
④症状が出た場合の受診
刺された場合は、「チクッ」と、とっても痛くて激痛が走りますので電気虫とも言われています。
私も知らずに触っていて2回も刺されました、あの痛さはもう忘れませんね。
一般的にはまず流水で刺された患部を洗い、皮膚に残った棘をテープで取り除きますが、針は小さくて私は目で確認ができませんでした。
次にステロイド配合の市販薬を塗布し、症状が5日以上改善しない場合は皮膚科を受診しましょうね。
嘔吐や腹痛、大量の発汗、呼吸困難などの症状が出た場合は、アナフィラキシーショックの可能性があります。
その場合は迷わず救急搬送を依頼してください。
早めの処置と受診が、重症化を防ぐ最善の方法です。
まとめ|イラガ つきやすい木と安全な庭づくりのために
イラガはカキやサクラ、キンモクセイなど人気の高い庭木にも付きやすく、刺されると強い痛みや炎症を引き起こします。
場合によってはアナフィラキシーショックなどの重篤な症状を招くこともあり、特に子どもやペットがいる家庭では注意が必要です。
発生サインを見逃さず、早期発見・早期駆除を心がけましょう。
冬場には繭や卵を除去し、春から秋にかけては定期的な薬剤散布や剪定で予防対策を行うことが効果的です。
「どんな木にもイラガは付く」という意識を持ち、日頃からの観察とこまめな手入れで、安全な庭環境を保ちましょう。